元ワーママのまぐです!
朝の支度、保育園の送迎、フルタイムの仕事、帰宅後の家事、そして寝かしつけ。
毎日がまるで「時間との戦い」で、気づけば自分のことを考える余裕なんてどこにもありませんでした。
それでも私は、ひとつだけ“譲らなかったこと”があります。
それが、毎月7万円の貯蓄と投資です。
「今は大変でも、未来の私と家族のために。」
そんな思いで、家計を見直し、節約を工夫しながら、投資の習慣だけは絶対に手放しませんでした。
この章では、子育てと仕事に追われる中でも資産を増やすために実践した節約術と家計のリアルを、私の経験をもとにお伝えします。
育児スタート。時間とお金が一気に消えていく現実
初めての育児は本当に手探りでした。
夜中の授乳、抱っこで寝不足、保育園の準備…。
「こんなに自分の時間がなくなるなんて」と何度も思いました。
それに加えて、お金もどんどん出ていきます。
オムツ、ミルク、洋服、そして保育料。

これまで自由に使えていたお金が、子どものためにあっという間に消えていきました。
それでも「投資だけは止めない」と決めた理由
そんな中でも、私は毎月7万円の投資は継続しました。
なぜなら、出産して改めて気づいたのです。
「子どもの将来のために、まずは私が経済的に安定していなきゃいけない」
自分に余裕がなければ、子どもにも心から向き合えない。
だからこそ、未来の安心につながる“積み立て投資”だけは、生活の中心に置こうと決めました。
節約のために、私がやった5つのこと
月7万円を確保するには、当然家計の見直しが必要でした。
そこで私が取り入れたのが、次のような節約ルールです。
我が家の節約ルール
- 食費の予算を1週間単位で設定し、買い物はまとめて週1回に。
- 固定費の見直し。格安スマホへ変更、不要なサブスクは即解約。
- 家計簿アプリを導入し、無駄な支出を見える化。
- 子どもの洋服やおもちゃはメルカリを活用。
- ポイント還元を最大限に活かした「楽天経済圏」への移行。

最初は少し面倒に感じましたが、習慣にしてしまえば自然と節約できる体質に変わっていきました。
我が家の家計ルールとリアルな予算公開
育休から職場復帰し、ワーママとしての日々が始まった頃。
家計は、夫婦それぞれが毎月生活費(私が5万、夫が10万)を共通口座に入れ、合計の15万円で生活費をまかなうスタイルでした。
保育園の費用(2万円)は夫の別負担。
そこから毎月の生活をやりくりし、私は自分の口座からは月7万円投資をキープしていました。
初めの頃は、共通口座の15万円で足りるのか不安でした。
でも、予算を明確にしておくことで、無駄遣いを防げる効果は大きかったです。
こちらが、当時の我が家のリアルな月の家計予算内訳です
(大人2人、4歳、1歳の4人家族)
| 項目 | 月額 | 備考 |
|---|---|---|
| 住居費 | 65,000円 | 賃貸マンション |
| 食費・日用品 | 50,000円 | 基本自炊、まとめ買い |
| 光熱費・通信費 | 20,000円 | 格安スマホ+電気・ガス・水道 |
| こども費(おむつ等) | 5,000円 | 楽天ポイント・メルカリを活用 |
| 外食・レジャー費 | 10,000円 | 月1回の外食+公園ピクニック |
合計:150,000円
特に食費と日用品は節約のしどころでした。
週に1度だけまとめ買いをすることで、無駄な外出や買い過ぎを防げましたし、
「冷蔵庫にあるものでやりくりする工夫」も身につきました。
また、格安スマホへの切り替えは、最初こそ不安でしたが、
実際には使い勝手も良く、月々5,000円以上の節約につながりました。
節約が“我慢”じゃなく“習慣”になるまで
最初は「節約って大変そう」「削るばかりで辛そう」と思っていました。
でもやってみると、意外と達成感がありました。
「今月も予算内におさまった!」
「今週は買い物に行かずに乗り切れた!」
「ポイントで生活用品をまかなえた!」
そんな“節約の小さな成功体験”が、日々のストレスの中でちょっとした喜びになっていました。
投資は“自動化”が最大の味方
日中は仕事と育児で手一杯。
でも投資は、証券口座に設定しておけば自動で積立してくれる。
この“ほったらかし”感が、私にはとても合っていました。
毎月の引き落とし通知を見るたびに「今月も未来に向けて投資できた」と、小さな達成感を感じていました。
積み重ねが自信に。お金の使い方が“生き方”を変え始めた
育児と仕事に追われながらも、資産が少しずつ増えていく感覚。
それが、忙しい日々の中で唯一“自分を保てる場所”だった気がします。
この頃から私は、「お金を貯めること」ではなく「お金を活かすこと」を意識するようになりました。
毎日、仕事、育児、家事に奮闘するみなさん。少し立ち止まってみませんか?
まずは、楽天証券で口座開設から始めてみませんか?
\\まずは口座開設//
⇒次回は【脱ワーママ計画|第3話】マミートラックの現実と、小1の壁。時短が終わる不安。へ
そして迎えた2人目の育休復帰。
待っていたのは、やりがいを失う“マミートラック”と心の葛藤でした。
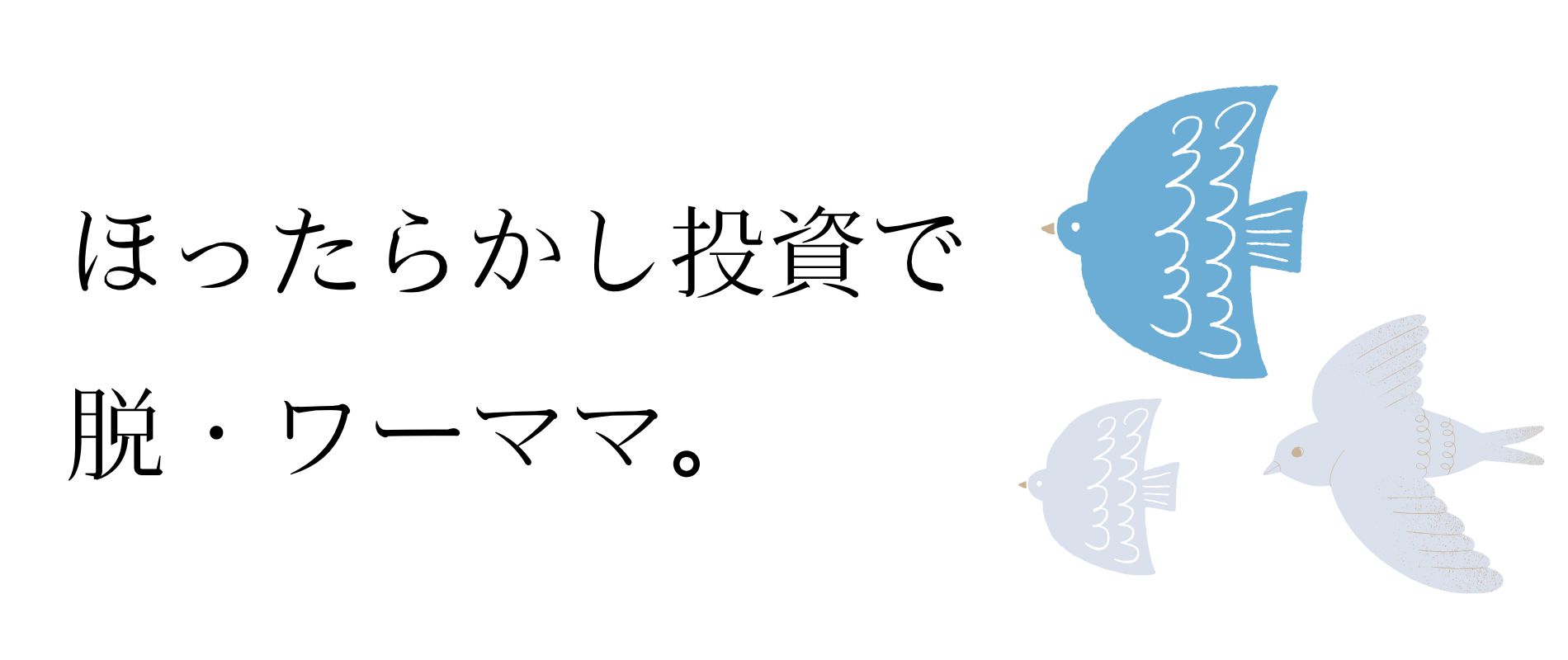
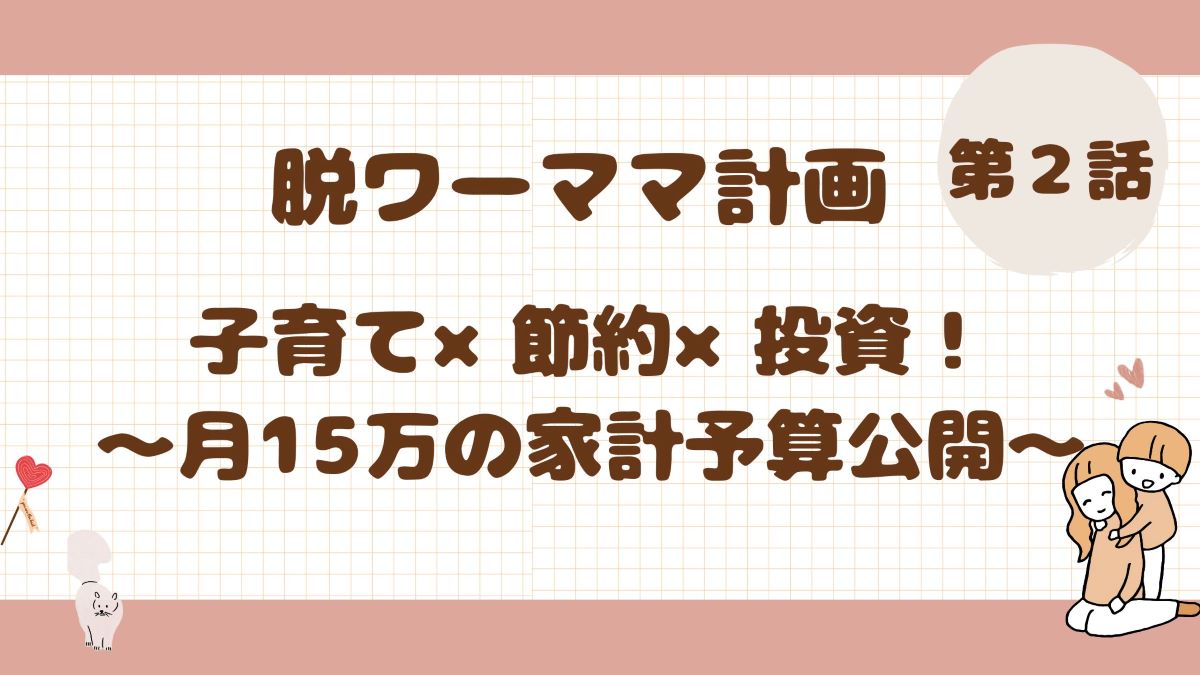

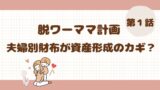





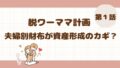
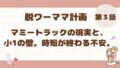
コメント